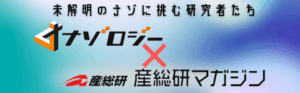※当サイトは、紹介している各ブランド・サービスの提供元企業とは一切関係のない、独立したレビュー・情報提供サイトです。掲載内容は当サイトが独自に調査・編集したものであり、各社の公式見解や保証を示すものではありません。
はじめに
今ではスマートフォンは大人だけでなく、子どもたちにとっても身近な存在になりました。小学生でもスマホを持っている子が増えていて、「うちの子にもそろそろ…」と考え始める親御さんも多いのではないでしょうか。
スマホはとても便利なツールですが、正しく使わなければトラブルの元になることも。今回は、子どもにスマホを持たせるときに親が気をつけたいポイントを、わかりやすくまとめました。

スマホを持つ小学生、あなたの周りにも増えていませんか?
実際に「連絡が取れて安心」「友達と話題が共有できる」といったメリットがある一方で、SNSトラブル・依存・課金などリスクも存在します。
この記事では、親として見落としがちな5つの落とし穴を取り上げ、それぞれのリスクに対する現実的な対処法をご紹介。
子どもとスマホの“ちょうどいい距離感”を見つけるヒントになるはずです。
子どもとスマホ、今どきの関係
最近では、スマホを持つ子どもがどんどん増えています。背景にはこんな理由があるんです。
- 共働きの家庭が増え、親子の連絡手段として必要になってきた
- GPS機能で子どもの居場所を確認できるという安心感
- 学習アプリなど、勉強にも使える便利なツールが増えてきた
- 周りの友達が持っていて、自分も欲しがるようになった
こうした理由から、スマホは今や“子どもにとっても必要な道具”になりつつあります。でも、便利なだけに、使い方次第では思わぬリスクも…。
だからこそ、親がしっかりと見守り、スマホとの付き合い方を教えることが大切です。
スマホを持たせるときの注意ポイント
1. 家族で「スマホの使い方ルール」を決めよう
スマホを渡す前に、まずは「どう使うか」について親子でしっかり話し合いましょう。たとえば…
- 使っていいのは何時から何時まで?
- 勉強中やご飯のときはスマホ禁止
- SNSの使用は許可制にする
- アプリ内課金は禁止する
ルールは親が一方的に決めるのではなく、子どもと一緒に考えるのがコツ。「なぜこのルールが必要なのか」を丁寧に説明することで、子どもも納得しやすくなりますよ。
2. フィルタリングやペアレンタルコントロールを活用
インターネットには子どもにとって危険な情報もたくさんあります。そこで役立つのが、フィルタリング機能やペアレンタルコントロール。
- iPhoneなら「スクリーンタイム」
- Androidなら「ファミリーリンク」
- 各キャリアが提供しているフィルタリングサービス
こういった機能を使えば、不適切なサイトやアプリへのアクセスをブロックできます。最初の設定は少し面倒かもしれませんが、子どもを守るためにはとても有効な手段です。
3. SNSは特に注意が必要!
LINE、Instagram、TikTokなど、子どもたちにとってSNSは「友達とつながる大事な場所」になっています。でも、気をつけないとトラブルに巻き込まれることも。
こんなことに注意が必要です:
- 顔写真や住所などの個人情報をうっかり投稿してしまう
- 友達同士のトラブルやSNS上でのいじめ
- 知らない大人とやり取りしてしまう危険性
SNSを使う場合は、アカウントの公開設定や投稿内容を親子で一緒にチェックしながら、正しい使い方を覚えていきましょう。
4. スマホ依存に注意!
気がついたらずっとスマホを見てる…なんてこと、ありませんか?子どもはまだ自己管理が難しいので、スマホに依存してしまうことも。
スマホの使いすぎが原因で:
- 視力が落ちる
- 睡眠不足になる
- 勉強に集中できなくなる
- 家族との会話が減る
といった悪影響が出ることもあります。スマホばかりにならないように、本を読んだり、外で遊んだり、家族で過ごす時間を大事にしていきたいですね。
5. 何かあったとき、すぐ相談できる関係づくり
どんなにルールを決めても、100%トラブルを防げるわけではありません。だからこそ、何かあったときに「すぐに話せる関係」を作っておくことがとても大切です。
「最近、何か困ってることない?」
「スマホのことで気になることある?」
こんなふうに、日ごろからさりげなく声をかけてあげましょう。ちょっとした違和感にも早く気づけるようになりますよ。
おわりに
子どもにスマホを持たせることは、今の時代においては自然な流れとも言えます。でも、その裏にはリスクもあるということを、親としてしっかり理解しておく必要があります。
大切なのは「与えるだけ」で終わらせず、どう使っていくかを一緒に考えること。ルール作り、見守り、会話を通して、子どもが安全にスマホを活用できる環境を整えていきましょう。