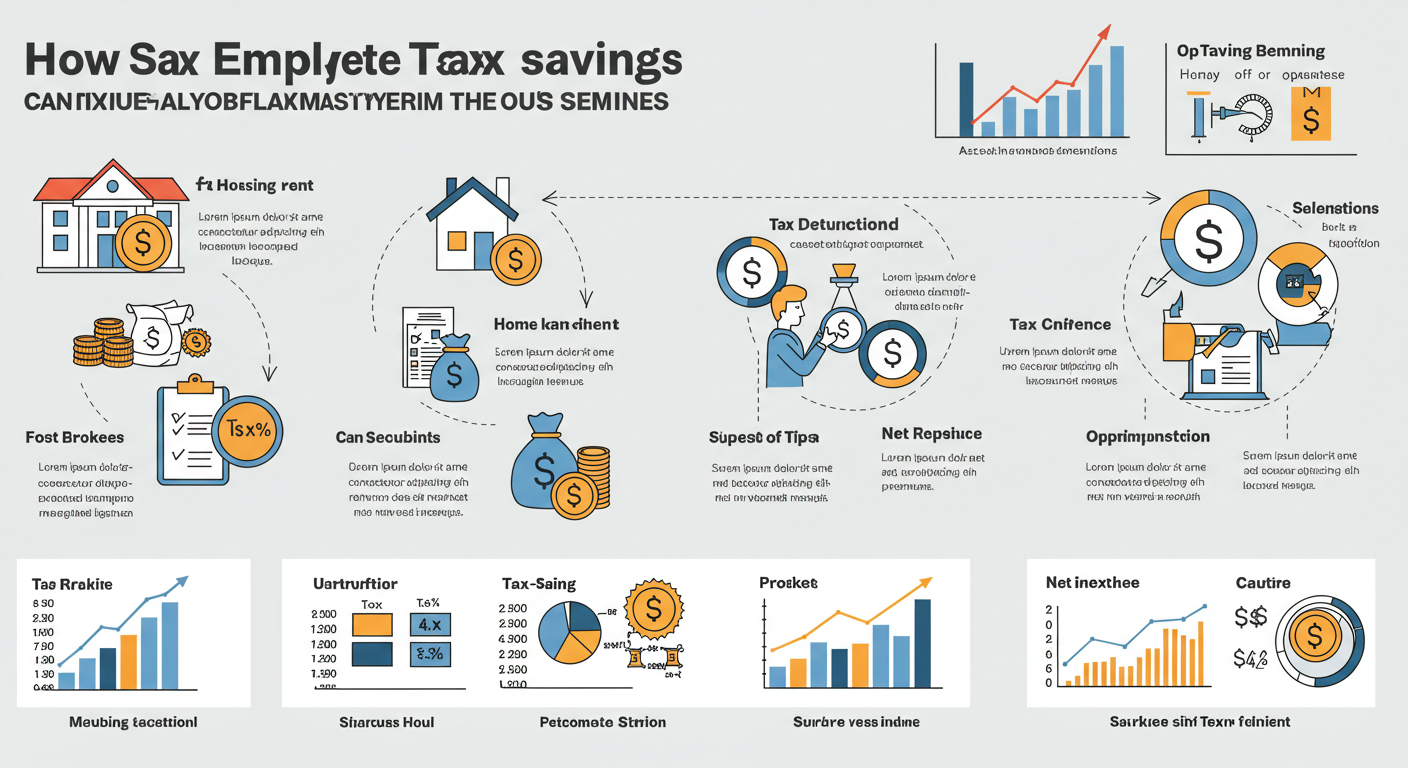節税は、それ自体が生活の質を損なうことなく、家計の助けになる手段です。
サラリーマンにとっても、給与から引かれる税金を少しでも減らす方法がいくつも存在します。この記事では、簡単に実践できる「サラリーマン向けの節税対策」を具体的にご紹介します。
目次
1. 保険を活用した節税
- 生命保険料控除 生命保険に加入している場合、支払った保険料に応じて所得から控除が受けられます。年間最大12万円までの控除が可能で、保険契約内容によって控除額が変わるので、契約書を確認し、必要に応じて見直しを行いましょう。
- 地震保険料控除 地震保険も控除の対象です。支払った保険料の全額が控除対象となるため、加入している場合は確定申告で申告を忘れないようにしましょう。
2. 投資による節税
- iDeCo(個人型確定拠出年金) iDeCoは、老後資金を貯めるための制度で、掛金が全額所得控除の対象となります。さらに、運用益も非課税で、節税しながら資産運用が可能です。ただし、60歳まで引き出せない点には注意が必要です。
- NISA(少額投資非課税制度) NISAは、年間一定額までの投資で得られる運用益が非課税となる制度です。つみたてNISAであれば、より長期的な資産形成に適しており、家計の負担を抑えながら投資を始められます。
3. 寄付による節税
- ふるさと納税 自治体への寄付を行うことで、2,000円を超える部分が所得税や住民税から控除されます。さらに、寄付先の自治体から特産品などの返礼品を受け取ることができるため、節税と同時に地域貢献も可能です。
- 一般の寄付金控除 NPOや公益財団法人への寄付も控除の対象です。寄付先によって控除額が異なるため、事前に確認しておきましょう。
4. その他の節税方法
- 副業の経費計上 副業収入がある場合、仕事にかかった経費を計上することで、課税所得を減らすことができます。例えば、パソコンやインターネット代など、業務に関連する費用が該当します。
- 特定支出控除 業務上必要な支出(通勤費、研修費など)で、一定の条件を満たす場合、給与所得控除に加えて控除を受けることができます。会社から証明書が必要な場合があるので、事前に確認しましょう。
5. 日常生活での節税
- 医療費控除 年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、その超過分を所得から控除できます。病院での診療費だけでなく、処方薬や通院のための交通費も対象となるので、領収書をしっかり保管しておきましょう。
- 住宅ローン控除 住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除されます。購入時に必要書類を整えておくとスムーズに手続きが進みます。
節税のポイントを押さえて家計をサポート!
節税は、知識を持ち実践することで家計に大きな影響を与える手段です。各種控除や制度を正しく活用して、無理なくお金を貯めることが可能です。この記事を参考に、ぜひ自分に合った節税方法を試してみてください。